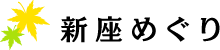『自然との対話、生命のエッセンス』
立教大学 観光学部交流文化学科 2年
大西 統眞
新座の緑豊かな風景に薄明かりが差す頃、私は静まり返った雑木林にいた。それは6月の夕方、空気は夏の大雨の名残で濃かった。土砂降りの雨でまだ光っている地面からは土の香りが漂い、濡れた葉っぱの甘い香りと混ざり合っていた。豪雨の後の静けさを取り戻した清らかな沢は、橙色と藍色の混ざった空を映し出し、自然の静かな回復力を幽玄な絵画のように描き出した。
立教大学新座キャンパスのすぐ近く、東三丁目駅からバスに揺られること約15分、堀の内橋というバス停に降り立った。「こっちこっち」。平成の名水百選を身で感じるべく共に冒険をすることになっただいちが、マップを見ながら言った。「少し蒸し暑いねぇ」。日中の大雨からか、夏の訪れを感じさせる湿気に、私の足は先をいそいだ。すぐに見えてきたのは、ゴーゴーとうなる黒目川。まるで湿気なんかに苛立ちを感じていた私を叱るかの様な勢いの川は、私とだいちが向うべき方向を示してくれた。川の両端にずらーっと連なる華やかな紫陽花たち。白、紫、青、赤、ピンク、そしてまた白、紫、赤、ピンク–まるで花信号の様な目を引く色のパターンと、シャワーを浴びた直後の水の滴る可愛さが私を歓迎してくれた。紫陽花に囲まれ、黒目川の流れに沿って小道を歩き続ける事20分、徐々に姿を現しだした木々。よく目を凝らすと川から分岐した水の流れがあった。その横には上の方へ伸びる木道、妙音沢の説明板。これが妙音沢の入り口だな。私は蒸し暑さも忘れ、上の方から来ているであろう水の音を頼りに木のスロープを登りだした。いや、体が勝手に進んでいた。何とも言えない雑木林の崇高さ。吸い込まれるように、私たちは迎え入れられた。夕方の薄暗さで、沈む日の光を吸収し、反射しながらその存在を知らせてくれる小さな川。さらさらと音を立てる流れのもとを辿ると、水が湧き出る水たまりの様な場所があった。透き通った水と、その水を守るごつごつまるまるした石ころたち、そして周りを、水たまりにお辞儀をするように生える雑草。かれらとの対面は、久しく感じたことのない、自然との対話であった。水の湧き出る姿は、自然が何かを語りかけてくるような気がした。そしてまた、私もどこか意思疎通が出来るような気がした。
目を閉じると聞こえてくる緑のシンフォニー–雨水の滴る音、葉のざわめき、遠くの鳥の鳴き声-が空気を満たし、沢の穏やかなせせらぎと調和していた。静けさの中のハーモニー。ああ––私はうっとりとその場に立ち尽くし、一日の最後を知らせる優しい光が水面で戯れ、静けさと時を超越した魔法にかけられていた。
「こんな感覚久しぶりだな」。居る事も忘れていただいちの声によってはっと目を開いた時、なんだろう。胸が軽くなっていたような気がしていた。胸の内を探してみたが、多忙な学生生活によって抱えんでいた精神的重圧が、どこにも見つからなかった。誰にも言わなかった悩み、疲れ。妙音沢との対話は、閉ざされた私の心を開いてくれた。この自然の回復力が私の中の箍を外し、心を開放してくれたのだった。
新座、妙音沢。この隠された小さな聖域の静ひつな美しさに包まれ、私は自然と魂の間の深いつながりを感じた。今となっては、私にとっての特別な時間である。